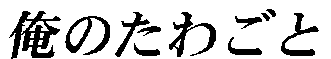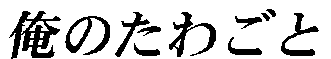あらすじ。
17才のある夏の日。
彼は憂鬱だった。
彼女が何度も家に来たいというので渋々、承知したのだが…。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ハァ…イヤだなぁ…。
絶対、彼女に良い印象は与えないだろうな…。
だって…。
ウチのオカンは…。
とてつもなく変なんだ。
「ここだよ…。」
「へぇ〜、ここなんだ〜!2階がタックンの部屋?」
「あぁ…。」
「どうしたの?元気無いね。アタシ、来ちゃマズかった?」
「いや、別にそんな事ないけ・・・」
「タックゥ〜〜〜ン♪」
「え…。」
母親が玄関から飛び出てきて彼の腕を掴み、ブンブン振っている。
「もう〜タックゥ〜ン!帰ってきたならいつものように抱きしめてよぅ♪」
「いつ…も…?」
「やめろってオカン!彼女が誤解するだろ!」
「えぇ〜?彼女??」
「あ、あのっ、私…やっぱり帰り…。」
「あ〜ら!彼女なのぉ〜??アンタもスミに置けないねぇ。じゃあ彼女、ウチへカモ〜ン♪」
「あ、いえっ、私…。」
「何を遠慮してんのよぉ〜(高音)入りなさいよぉ〜っていうか入れ。(低音)」
「…ハ、ハイ。」
「彼女を脅すなよオカン!怖がってんじゃねぇか!」
「あらぁ〜そんなの冗談ってわかってるわよねぇ〜?そうよね〜?」
「ハ、ハイ。」
「ア?ビビってんのか?(低音)」
「いえ!ビビってないです!」
「そうよねぇ〜!(笑)オホホホホ。」
「と、とりあえず俺の部屋に行こうぜっ。」
「う、うん。お邪魔します…。」
「待ちなさい、タックン。ちょっと彼女、タックンの部屋に行っててね〜。二階の奥だから〜。」
「あ、ハ、ハイ…。」
「なんだよぉ〜もぉ〜。」
母親は彼の耳元でこう囁いた。
「もうヤったの?」
「ハァ?」
「とぼけんじゃないわよ〜。高校生でしょ〜?パンパンでしょ〜?」
「なっ、なに言ってんだよ!」
「KGBで表して!」
「なんだよKGBって!」
「Kかなり、Gギリギリ、B別に。」
「聞いた事ねぇよ、そんな区分け!」
「いいから!早く!危ない!」
「何も危なくない。なんなんだよもう〜!」
「お願いタックン…。アタシ、答えてくれるまで離さないんだから!絶対別れないから!」
「何のドラマだよ!俺はオカンと付き合ってないから!」
「そうやって無かった事にするのね…ヒドイ…。」
「もう〜メンドクセェよぉ〜!」
「で?早く早く!彼女は部屋でお待ちかねですぜ、ダンナ!」
「今度は誰だよ。キャラを一つに絞れよ。」
「早く言ったらいいじゃない。そんなの普通の会話よ。バカねぇ。」
「B。」
「え?」
「だからBだってば。」
「Bまで…行ったのね?」
「さっきとニュアンスが違うじゃねぇか!別にまだ何もしてないって!」
「まだ、って何よ。イヤらしい子!そんな息子に生んだ覚えは無いわよ!」
「自分で聞いたんじゃねぇか!」
「息子が…ムスコをおっ立てて…。母さんは恥ずかしい!」
「ホントに恥ずかしいよアンタ。」
「まぁいいわ。差し入れするから部屋行きなさい。」
「あ、ホントに?サンキュ。」
彼はふぅ〜っと溜め息をついて部屋に入っていった。
彼女は正座をして待っていた。
「あっ、そんなかしこまらなくてもいいのに!ウチのオカンはちょっと変なだけで、
あれでも面白くてやってるつもりだから気にしないでいいよ、ハハハ…。」
「ユ…ユニークなお母さんなんだね。」
「ちょっとはしゃいでるだけだから…。あ、そうそう。何か差し入れるってさ。
もう大丈夫だよ。マトモになってるはずだから。冷めんのも早いんだ、あの人。」
「そ、そうなんだ…。」
「あ、そうだ!写真見る?写真!ほら、前に俺のアルバム見たいとか言ってたじゃん!」
ガチャ ドサッ
一瞬、部屋のドアが開いてエロ本が投げ込まれた。
「オイ!オカン!何やってんだよ!」
ガチャ
「だって、写真が見たいって言うから…。」
「アンタは妄想し過ぎだから!もういいから出てってくれよ!」
「そぉ?今日は冷たいのねぇタックン。」
「いいから早く!」
「あ、そうだ。差し入れよ。ホイ。」
それは小さな四角い箱だった。
「ミチコ…ロンドン…?」
「避妊はしときなさい。その子を大事に思うならね。それが姉さんの願いよ。」
「姉さんじゃないし!いいよもぉ〜!」
「あ〜ら、彼女はあった方が安心って顔をしてるわよ、タックン。ほら。」
そこには顔を真っ赤にした彼女が居た。
「へへ〜ん!騙されタックン!騙されタック〜ン!じゃあね〜!」
バタン!
数分間の沈黙。
二人は向かい合って座り、ずっと黙っていた。
彼女はめっちゃ意識してる表情。
彼はその空気に耐えられず、彼女に話し掛けた。
「あ、あの…。」
「ちょ、ちょっと待って…。」
彼女は顔を赤らめたままだった。
「いや、そういうんじゃなくて!」
「違うの!」
「お母さんは出掛けるからいいのよ。タックン。おっぱじめなさい。」
「アンタいつ入ってきた!」
「お父さんにもそんな純な頃があったっけ…。」
オカンはそう言ってタバコを吹かす素振りをした。
「もういいから!出てけ!」
「ココはアタシとサトルさんの家よ!このドロボーネコ!」
「そういう問題じゃないから!」
彼は立ち上がり、母親を部屋から押し出した。
振り返ると彼女はクスクス笑っていた。
「お母さん、面白い人なんだね。」
「厄介なんだよ〜お客さんが来るとはしゃいじゃってさぁ…。」
二人で顔を見合わせて笑った。
それからは空気が和んで楽しく会話が出来た。
オカンは本当にどこかに出かけたようだった。
そして数時間後。
ミチコロンドンは役に立った。
夕食の時、オカンが突然、俺にこう聞いた。
「上手く行った?」
親指を立てて成功の合図をすると、
オカンはクスッと笑って親指を立て、こう言った。
「良かったじゃん。」
2005/06/20

|