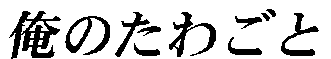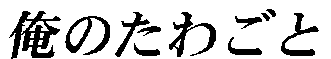これは俺のたわごと『変なお母さん』シリーズのお話。
まだ読んでない人は先に読んで来やがれってんだ。
--------------------------------
今回の話は昔の話。
タックンが8歳の時の話だ。
怖いTVを見てなかなか寝付けないタックン。
居間に行くと、お母さんと目が合った。
--------------------------------
「どうしたの、タックン。寝れないの?」
「なんか怖いTVがやってたんだもん。」
「じゃあ、お母さんがお話をして寝かし付けてあげるー。」
「うん!」
2人はタックンの布団に横になった。
「じゃあねぇ…はなさかじいさん!」
「はなさかさんって人なの?」
「違うわ。花を咲かせるおじいさんのお話なの。」
「おぉ〜。すごい!」
「拍手〜。」
「パチパチパチパチー。」
「むかーし、むかしの事じゃった。」
「あ、始まった。」
「あるところにおじいさんとおばあさんがおったそうな。」
「・・・・・。」
「めでたしめでたし。」
「終わっちゃダメー!」
「終わっちゃった。ダメなの?」
「ちゃんと話してよぅ〜!」
「しょうがないわね。」
「寝れないでしょ。」
「おじいさんが街に行く途中、オナカを空かせた子犬がおりました。」
「うんうん。」
「おじいさんは捨て犬を拾うほど優しくなかったので、華麗にスルーしました。」
「華麗にスルー?」
「見捨てたってことよ。」
「なんで?かわいそうだよぉ!」
「どうして?」
「だって、オナカ空かせてるんでしょ?」
「あのね、タックン。世の中にいる全ての動物を救ってるとね、バランスが崩れるの。」
「バランス?」
「みんな長生きしたら地球は動物で溢れちゃうでしょ。」
「それでいいじゃん!」
「食べ物の奪い合いで戦争が起こるのよ。ますます飢え死にする人が増えるわ。」
「もっといっぱい食べ物を作ればいいじゃん!」
「動物同士が食べたり食べられたりしてバランスが取れるの。」
「でも・・・。」
「タックン、ハンバーグ好きでしょ?」
「え?・・・うん。」
「あれ、牛さんと豚さんじゃない。」
「あ・・・そうか。」
「牛さんと豚さんは死んでもかわいそうじゃないのね?」
「・・・かわいそう。」
「じゃあハンバーグは食べられません。」
「やだー!」
「どっちかにしなさい。食べるの?食べないの?」
「・・・食べる。」
「あ〜ぁ、かわいそう。ブーブー、モーモー、泣きながら死んでいく動物たち。」
「やだ〜!!言わないでよ〜!ワ〜ン!!!」
泣き出したタックン。
「タックン、生きてる限りは他の命を貰う事になるの。」
「・・・うん。」
「だからね、その命の分まで精一杯生きるの。」
「・・・わかった。」
「じゃあ子犬はどうするの?」
「・・・見捨てる。」
「ダメよ、タックン。子犬がかわいそう。」
「だって、さっきお母さんがそう言ったじゃん!」
「おじいさんも子犬に優しくしたい時があるのよ。」
「・・・わかった。」
「おじいさんは子犬を拾いました。」
「良かった。」
「おじいさんは子犬を家に連れて帰りました。」
「うん。」
「おじいさんの家ですっかり元気になった子犬はどんどん成長していきました。」
「名前は?」
「名前って?」
「子犬の名前。」
「犬は犬よ。名前なんか付けないの。」
「なんでー!?つけようよー!」
「じゃあアルキメデス。」
「そんな変な名前やだー!普通の名前がいいー!」
「歴史に残る数学者をバカにしないでちょうだい。」
「知らないもん!」
「じゃあしょうがないわね。シロでいいわ。」
「うん。シロならいいよ。」
「えーと、どこまで話したっけ。」
「シロは元気になりました。」
「あぁ、そうね。それである日、シロはおじいさんを裏山に連れて行ったの。」
「うん。」
「そして、シロはココ掘れワンワンって言ったの。」
「喋ったの?」
「ううん。本当は喋ってなかったの。おじいさん、すっかりボケちゃってたのね。」
「そうなんだ・・・。」
「昔はすごくハキハキした人だったんだけどね・・・。」
「かわいそうだね。」
「タックン。かわいそうって言うのも、失礼になる事があるのよ。注意してね。」
「なんで?」
「そんな風に言われると、逆に自分がみじめに感じちゃう人もいるの。」
「・・・わかった。」
「それでね、えーとなんだっけ。」
「ココ掘れワンワン。」
「そうね。ココ掘れワンワンと言われたおじいさんはどうしたと思う?」
「そこを掘った。」
「ブブー!まずはシロが喋った事を不気味に思ったの。物の怪の類だと思ったのね。」
「物の怪って?」
「オバケとか妖怪みたいなモノよ。」
「なんで?」
「だって、普通に考えりゃ犬が喋れるわけないでしょうよー!」
「あ、そっか。」
「でも、掘りました。」
「掘ったの?」
「だって、逆らったらどうなるかわからないでしょうよー!」
「あ、そっか・・・。」
「そうよ。シロは地獄の番犬・ケルベロスかもしれない。」
「ハリーポッターに出てきたヤツ?」
「そうそう。あんなのに逆らえるじいさまじゃないわ。」
「シロ怖いね・・・。」
「で、じいさんが掘ると、そこからは大判小判がザクザク出てきました。」
「すごい!やったね!」
「でも、そこはおじいさんの土地ではなかったの。」
「え?裏山が?」
「そうよ。その辺は全部地主さんの土地なの。」
「・・・うん。」
「おじいさんの家も地主さんの土地を借りてるのよ。」
「そうなんだ。」
「でね、残念なんだけど埋蔵物は土地の所有者にも権利があったのよ。」
「マイゾウブツ?」
「その土地に埋まってたモノね。」
「・・・うん。えっ、おじいさんはお宝を取られちゃったの?」
「そう。現在の法律だと発見者と半分ずつなんだけど、当時はそうじゃなかったからね。」
「おじいさんかわいそう・・・。」
「しかも、バケモノ犬に怯えながら暮らす事になるわけよ。」
「大変だね・・・。」
「ところが、隣の家のおじいさんが犬を貸せと言って来たの。」
「なんで?」
「自分も宝を掘り当てたかったのよ。」
「バケモノなのに?」
「欲っていうのはね、時に人を変えてしまうの。怖いわね、タックン。」
「うん・・・。」
「で、隣のおじいさんが自分の土地にシロを引きずっていきました。」
「え〜、バケモノ犬を引きずって?」
「怖いもの知らず、ってか後先考えないバカなのよ。」
「ふーん。」
「そしたら掘っても掘っても小判は出ず、ミミズやヘビしか出ませんでした。」
「あ〜あ。」
「怒った隣の家のおじいさんはシロを殺してしまいました。」
「えっ・・・。」
「ところが、これが法律に触れたのね。」
「そうなの?」
「生類憐みの令。犬が大好きな将軍が作った法律でね。」
「破ったらどうなるの?」
「死刑。」
「えっ。」
「さらに、犬を殺した人をチクると30両がもらえたの。」
「じゃあ誰かがそれを言ったの?」
「そう。もちろん、シロの飼い主のおじいさんよ。」
「シロを怖がってたのに?」
「お金がもらえりゃ別なんでしょ。大判小判は没収されちゃったし。」
「おじいさんもヒドイね。」
「そうね。タックン、このお話でわかったでしょう。人間の欲は怖いものなの。」
「うん、わかった。」
「そう、じゃあそろそろ寝なさい。」
「えっ?だってまだ・・・。」
「なにかあるの?」
「花を咲かせてないよ?」
「・・・その30両で女の子を引っ掛けて、老後にひと花咲かせたそうよ。」
2007/05/19
|