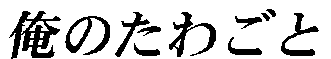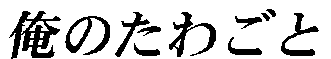ある若者が捨て猫を見つけた。
その猫はすぐに人に噛み付く猫だった。
だが若者はその猫が臆病で気が小さいから人に懐かないのだと悟った。
若者はその猫を飼うことにした。
村人は「あんたも酔狂な真似をしなさるなぁ。」と口々に言った。
若者はそんな事はおかまいなし、気にも留めなかった。
むしろ、「この猫を飼う事が出来るのは自分をおいて他に無い。」とさえ思った。
その日から一人と一匹の生活が始まった。
若者には他に飼っていた猫が一匹居たが、
この猫が心を開いてくれるためにはこの猫を遠ざけるしかないと思い、
他人に譲り渡した。
そうまでしてでもこの猫が飼いたかったのだ。
若者はこの猫の心の傷が何であるか知りたかった。
臆病になってしまった原因、心を開かなくなった原因が何であるか。
そしてその傷を癒してあげたかった。
しかし月日が経とうとこの猫が懐く事は無かった。
何度か膝元に擦り寄っては来たのだが、若者が撫でると爪を立てた。
若者はそれでも撫でた。
若者の腕はその猫の引っ掻き傷と噛み付かれた傷が絶えなかった。
村人達は「なんだかんだ言ってあの猫もあなたに懐いてるようだね。」と言うようになった。
しかし、逆に若者は徐々に自信を失いつつあった。
俺ではこの猫の心を開かせる事は出来ないのかもしれぬ、と。
そんなある日の晩、若者の家に訪ねて来た者がいた。
彼はつい先日、都から帰って来たのだと言う。
彼は若者にこう言った。
「共に都で勉学に勤しもう。おまえはこんな田舎で潰れていくには勿体無い男だ。」
若者が迷っていると彼はさらに続けた。
「私の師におまえの事は話しておいた。既に宿も用意してくれている。」
若者は悩んだ末にこう言った。
「確かに、このままのんべんだらりと日を送っていては両親にも面目が立たぬ。
よし、では明日になったら俺を都に連れて行ってくれ。」
これを聞くと彼は喜び、
「そうこなくては。よし、では明日の朝迎えに来るぞ。」
と言い残して足早に帰っていった。
若者は囲炉裏の前に腰を下ろし、酒を飲んだ。
今後の事を色々と思い巡らせた。
ふと横を見ると猫が居た。
若者は猫に語りかけた。
「俺は明日、都に行く。おまえは一緒に来てくれるかい?」
猫は何も言わず、部屋を出て行った。
「つれないものだな。ここまで懐いてもらえないとは。」
若者は溜め息をつき、床に入った。
翌朝、若者が目覚めた時には猫は居なくなっていた。
若者は近所を探した。
それでも猫は見つからない。
仕方なく家に戻ると友人が迎えに来ていた。
「遅いではないか。待ちくたびれたぞ。」
若者は「猫が見当たらないのだ。」と彼に言った。
「猫なんてまた飼えばいいではないか。都にも猫はいるぞ。」
確かにそうだ。
だが、若者は思った。
あの猫の心を開けるのは自分しかいない、あの猫を見捨てていくわけにはいかない、と。
「おまえが探しているのはあの猫ではないのか?」
友人の指す方向に若者が目をやるとあの猫が居た。
若者は猫の元に駆け寄り、優しくこう言った。
「おまえも共に都に行こう。」
猫にはわかっていた。
この若者の言葉も。
どれだけ優しい人なのかも。
猫にとってこんなに人間に優しくされるのは初めてだったのだ。
猫は付いていきたかった。
しかし、もしまた捨てられたらと思うと怖かった。
そして猫は―
若者の手を引っ掻き、逃げて行った。
若者は寂しそうな表情をしていた。
その顔を物陰から見た猫は主人の元に駆け寄りたい衝動に駆られた。
しかし、猫は最後まで意地を通したのだ。
寂しい気持ちを押し殺して、主人の後ろ姿を見守っていた。
若者は友人に促され、都へ向かっていった。
「結局、懐いてくれなかったな…。」
若者はそう呟いた。
猫はそれ以来、飯を食うことも無しに主人の帰宅を待った。
本当は「一緒に来てくれるか?」と言われた時は嬉しくてしょうがなかった。
しかしその反面、この先もしも彼に捨てられるような事になったら、もう立ち直れなくなる、とも思った。
もし、帰ってきたらその時は素直になろう。
ずっと一緒に彼と暮らしていこう。
あの人はずっと優しくし続けてくれていたんだ。
彼が迎えに来てくれたら飛びついて甘えよう。
そう心の中で思いながら、猫は待った。
しかし、主人が帰る事は無かった。
猫はそのまま飢えて死んでしまった。
主人は三年後、故郷に帰ってきた。
そして家の玄関に転がる猫の骨を見て嘆き悲しんだ。
若者は「何もわかってやれなかった。」と泣いた。
ようやく一人と一匹の心は通じ合ったのだ。
2003/09/08
|