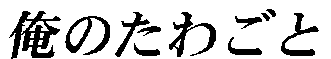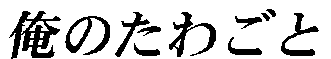彼には恋人がいた。
付き合って5年になる可愛い恋人が。
その日、彼は彼女とランチの約束をしていた。
お互い、同じオフィス街に職場があるので、
たまに待ち合わせてランチを一緒に食べるのだ。
今日は彼の方が早く着いた。
待ち合わせ場所のオープンカフェでココアを頼み、
彼は彼女を待つ事にした。
「ご注文のココアです。」
若いウェイトレスがココアを持って彼のテーブルに来た。
「ごゆっくりどうぞ。」
ココアの入ったマグを持ちながら、ボーッと街を眺めていると、
風船を持った男の子とその母親らしき女性が目に入った。
『オフィス街にしては珍しい光景だな。』
彼はなんとなくその二人を目で追っていた。
次の瞬間−−
パーンという風船の破裂音と共に時間が止まり、世界はモノクロになった。
彼は驚き、思わず立ち上がった。
まるで白黒写真の中にでも閉じ込められたかのようだった。
街行く人も全て止まっている。
ウェイトレスが注いでいるコーヒーすらもそのままに宙で固まっている。
「哀れなるかな、人の子よ。この世界に迷い込むとは。」
頭の中に直接、声が響いて来た。
「誰だ?オマエは誰だ?」
彼はキョロキョロと辺りを見渡した。
後ろを振り返ると、モノクロームの世界に赤い色がぽつりと見えた。
そこには赤い首輪を付けた猫がいた。
世界は止まっていたが、その猫だけは動いていた。
シッポをピンと立て、猫は彼を見上げていた。
「我輩は猫である。名前はもう無い。」
その猫はゆっくりとそう言った。
「もう無い?」
「呼ぶ者が居なければ名前など無くなる。」
猫は目を閉じてそう言った。
「おい、オマエは【この世界】と言ったな。ここはなんなんだ?異次元か?」
「この世界か。人の言葉で言うならば走馬灯のひとコマの世界だ。」
「走馬灯?死ぬ寸前に見るというアレか?」
「そうだ。」
「俺は死ぬのか?」
「まだ決まっていない。だからココに来た。」
「決まってない?」
「そうだ。」
「勝手に人をわけのわかんねぇ世界に引きずりこむな。帰らせろ。」
「我輩が呼んだ訳ではない。オマエが勝手に来たのだ。
我輩はたまたまココに居合わせただけのこと。」
「オマエがこの世界に来させたんじゃないのか?」
「オマエがどうしてこの世界に迷い込んだかは我輩の知る所ではない。」
「どうすれば出られるんだ?」
「出るのは簡単だ。その前に一つ、言っておく。」
「なんだ?」
「オマエはこれからすぐに恐ろしい光景を目にする。」
「恐ろしい光景?」
「そうだ。その時、運命を変えたければ我輩を呼べ。選ばせてやる。」
「運命を?」
「その代わり、オマエの命が代償だ。」
「なんなんだ?ワケがわからねぇよ。」
「運命を選べるだけ運が良いと我輩は思うがな。」
その次の瞬間、彼の周りの世界が動き出した。
色もちゃんと付いている。
「戻った…のか?」
彼はボーッとその場に立ち尽くしていた。
ふと顔を上げると、遠くに彼の恋人の姿が見えた。
彼女はまだこちらに気付いていないようだった。
「夢だったんだろうか…。」
次の瞬間−−
パーンという風船の破裂音と共に地面が揺れ始めた。
「地震…?」
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ
揺れはどんどん激しくなり、立っているのがやっとの状態になっていた。
高層ビルは次々と壊れていき、ガラスやコンクリなどの破片が落ちて来た。
その破片は車や信号機、街灯や人々に襲い掛かった。
もの凄い轟音と人々の悲鳴で耳がおかしくなりそうだった。
彼は彼女の元に駆け出した。
「危ない!早く避難するんだ!」
彼は大声で彼女に向かって叫ぶ。
その時、彼女の足元に亀裂が走り、地面が裂けて彼女は落ちた。
「キャ-------ッ!」
彼女の下半身がそこに挟まり、身動きが取れなくなってしまった。
さらに彼女の真上に大きなコンクリートの塊が落ちて来た。
ゴシャッ!!!!
コンクリートの塊は彼女を直撃し、彼女は無残にも下敷きになった。
頭蓋は砕け、見るも無残な死に方だった。
彼はその場にガックリと膝をついた。
「ウソだ…。」
「ウソだ…。」
「ウソだ…。」
地震はそれからしばらくしておさまった。
辺りは人の気配が無くなっていた。
彼以外に無事でいる人間は一人も居ないようだった。
彼は呆然と立ち尽くしていた。
10分、いや20分ほどだろうか。
彼は呟いた。
「猫よ…俺だ…。」
さっきの猫の事を思い出したのだ。
「…聞こえているんだろう。」
「…俺の命をくれてやる。」
猫は目の前の何も無い空間から姿を現した。
「オマエの命の重さでは時間を巻き戻し、大地震を止めるのが精一杯だ。」
「…あぁ、それでもいい。」
「自分の命は無くなる。それでもよいか?」
「あぁ…頼む。早く終わらせてくれ。」
「…わかった。」
そして、眩しいほどの光が辺りを照らした。
光源は彼自身だった。
瓦礫は舞い上がり、人々は起き上がり、地面の亀裂は塞がっていった。
時間がゆっくりと戻っていったのだ。
そして、全てが元通りになった。
「ご注文のココアです。」
若いウェイトレスがココアを持って彼のテーブルに来た。
「ごゆっくりどうぞ。」
遠くに彼女の姿が見えた。
彼は立ち上がり、彼女の方を見て微笑んだ。
パーンという風船の破裂音と共に彼は息絶えた。
2005/12/29
|