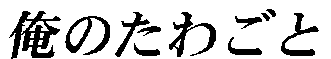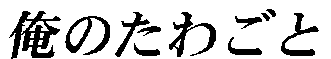猫は好きだった。
ノラ猫は好きだった。
小さい頃は近所にノラ猫がいっぱい居た。
普段は人を見ると逃げるのだが、夜になると寄って来る猫が多かった。
寒いから懐いてくるのだ。
昼に寄ってくる猫はめったに居なかったので、たまにそういう猫が居ると貴重だった。
黒の虎毛で緑色の目をした猫もその一匹だった。
俺達は小学四年生の頃にその猫に出会った。
近所の子たちと一緒にその猫に『グリーンアイ』と名を付けた。
エサをあげたり撫でたりしていた。
しかし、俺達は団地暮らしだったので夜になったら逃がさなくてはならない。
次の日になったら遊べる保証は無い。
俺達はそれがイヤだった。
ある時、粗大ゴミに風呂の浴槽が出してあった。
団地の人が出したモノらしかった。
追い焚き用の穴が2個空いているモノだった。
俺達はそこに猫を入れて牛乳とエサを置いておいた。
寂しそうに泣いたので少し心配したが、寒い外よりはマシだと思ったのか、
しばらくするとおとなしくなり、横になっていた。
俺達はそのまま家に帰って行った。
そして次の日の朝。
隣の家の子が朝早くにウチに来た。
「有ちゃん!ネコが大変だよ!」
俺と兄貴は何事かを確かめるため、すぐに外に出た。
すると、ヤツは追い焚き用の穴に首を突っ込んでハマってしまっていたのだ。
俺は両手でゆっくり外そうとしたが、完全にハマって取れなくなっていた。
「ダメだ。アゴの骨の辺りでつっかえてる。」
セッケンなどでヌルつかせて取る案も出たが、猫の体に良くないかも、と却下した。
俺達が色々と対策を考えていると親父がやってきて言った。
「切っちゃえばいいじゃん。」
俺達はビックリして言った。
「ナニ言ってんだよ。出来るわけないじゃん。」
っていうか、普通に死ぬじゃんソレ。
風呂釜から取れればいいとかいう問題じゃないから。
『またこの人はフザけてこういう事を言って…』などと思っていた。
親父は黙って家に入って行った。
俺達はまた思案し始めた。
少しして、親父が家から出てきた。
手には糸ノコを持っていた。
「ダメだよ!猫が死んじゃう!」
俺達は慌てて親父を止めようとした。
親父は笑って「アッハッハ。そんな事をするわけないだろ。」と言った。
そして猫の頭を少し下げて「ゴメンな。少し我慢しろよ。」と言って隙間に糸ノコを入れた。
親父は実に器用にその穴を上に広げて猫を出す事に成功した。
俺達は親父にお礼を言った。
「ありがとう。俺たちが不注意なばかりに。」
親父は諭すように言った。
「ココに入れるなら穴を塞いでやれ。でも、ノラなんだから閉じ込めるのは可哀想だ。」
俺達は少し遊んだ後、猫を逃がしてやる事にした。
また、小学五年生のある日、俺は隠れんぼをしていた。
その時、俺は友達と二人で自転車置き場に隠れていた。
すると、どこからか「ミィミィ」という子猫の鳴き声が聞こえて来た。
俺と友達で顔を見合わせ、お互いの声ではない事を確認し、
辺りをキョロキョロとして子猫の姿を探してみた。
それはホウキなどが入れてあるポリバケツの中から聞こえていた。
俺達はゆっくりとそのポリバケツを覗き込んだ。
その瞬間、親猫が「ミャアア!」と大きい泣き声とともに飛び出してきた。
俺達はビックリして「ウワァ!」と声を上げてシリモチをついた。
親猫はそのまま塀の上に逃げていった。
そしてポリバケツの中を見てみると生まれたばかりの子猫が4匹いた。
「生まれたばかりだ!ココで産んだんだな。」
俺達はその子猫たちを触ろうと思ったが、親猫が心配するだろうと思い、やめておいた。
そして少し離れた所から様子を伺っていた。
親猫は辺りを伺いながら戻ってきた。
そして一匹ずつ口に咥えて塀の上に連れて行った。
それからしばらくして、俺達が自転車置き場の裏で遊んでいると、
また、どこからか「ミィミィ」という子猫の鳴き声が聞こえて来た。
俺達はその鳴き声を真似てみた。
「ミィミィ。ミィミィ。」
すると塀の上から親猫が「フーッ!」っと怒りながら走ってきた。
俺達はビックリして逃げ出した。
多分、親猫は子猫がさらわれたと思ったのだろう。
普段は人に寄り付かないその猫は20mほど追いかけてきた。
俺達は逃げた後、「これは面白い。」と何度も子猫の鳴き真似をして逃げた。
3回ほど親猫は追いかけてきたが、その後は全く姿を現さなくなった。
子猫を連れてどこかに移動してしまったようだった。
親猫の子猫に対する愛情を垣間見た気がした。
猫の世界でも親はやはり親なのだ、と思った。
高校一年生の頃、Saityの当時の彼女の家に遊びに行った。
その子の家は猫を飼っていた。
遊びに行ったのは寒い時期だったと思う。
俺は石油ストーブの前であぐらをかいていた。
すると、その猫は俺の膝の上に乗って寝始めた。
「無邪気でカワイイねぇ。」と言いながら俺はその猫を撫でていた。
しばらくして、俺はトイレに行きたくなった。
「あの、スイマセンけどトイレに行かせて下さいます?」
俺は猫にそう語りかけながら猫を移動させようとした。
その時、ヤツは俺の指を思いっきり噛んできた。
俺はビックリして肝が縮んだ。
それからは猫に対して警戒するようになった。
月日は流れて23歳の時、同棲していたカナの実家に行った。
カナの実家にはチーズという猫がいた。
この猫は恐ろしい猫で、俺を見ると毛を逆立てて戦闘体勢に入るのだ。
カナが一緒に居る時はあまり襲ってこないが、カナが少しでも離れると襲ってきた。
カナが去った方向を名残惜しそうに見てから、すぐにこちらを振り返り、
「アンタ、覚悟しぃや。」とでも言いたげに俺を睨みつけ、足元を狙って飛び掛ってくるのだ。
俺は何度もカナの実家に遊びに行ったが、この猫をマトモに撫でた事は一度も無い。
カナが抱いている時に俺がヤツの死角から背中を撫でても、
「あん?テメェ、今触ったろコラ。」とでも言いたげに睨んでくる。
一度、俺が掃除機をかけている時にヤツを撃退して確執は決定的になった。
その後は俺もなるべくヤツに近づかないようにしていた。
この猫のお陰で俺は猫が嫌いになった。
そして最近、赤井の家で猫を飼い始めた。
保健所に行って貰って来たらしい。
レオという名の猫だ。
このレオはあまり人見知りをせず、そうそう人を噛んだりもしない。
生まれて間も無いので噛まれてもそんなに痛くないし、
「レオ!」と叱るとちゃんと噛むのをやめる。
そして子猫だから遊んでやると大はしゃぎする。
俺が構ってやると際限なく遊び続けるのだ。
ただ、俺が寝ている時に顔の前に来て寝るのは愛らしいが少しやめていただきたいが。
しかし、俺はレオに会ってから猫がまた好きになってきた。
レオだったら一緒に住んでもいいかな、と思う。
今度、遊びに行く時はオモチャでも買っていってやろうと思う。
そんなこんなで、今では猫が好きだ。
2005/04/07
|